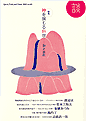| ![editor's note[after]](../no75/img/editor_after.gif)
私たちは、なぜ科学を選ぶのか。
若すぎる科学、科学者の役割
「環境の分野は、科学としてまだ若すぎるんですよ」。開口いちばん渡辺正氏の口から飛び出したのはこんな言葉だった。生まれてまだ半世紀もたたない科学であれば、いろいろな解釈が出てきて当然である。新しい発見だってまだまだあるだろう。時には勇み足になって、間違った見方をすることもあるかもしれない。どれもこれも、結局のところこの科学がいまだ発展途上にあるゆえのことなのだ。その意味ではダイオキシン問題もほかの環境問題と同じである。しかし、ダイオキシンがほかの地球環境問題と一線を画すのは、そのシロ/クロがまだはっきりしない段階で、法律にまでなってしまったことである。そして、国民に厖大なつけ(財政負担)をおしつける結果になった。ダイオキシンは、科学でのきちっとした議論を経ずに、一気に社会の問題になった。そこに、ダイオキシン問題の看過できない理由がある。
『ダイオキシン 神話の終焉』は、発売と同時に大きな波紋を広げた。にもかかわらず、新聞や活字メディアが比較的好意的だったのは、一つには、利権構造と環境行政が結び付いているところを暴き出したことが大きい。ダイオキシンをネタにした環境スキャンダルだとはっきりと指摘した識者もいた。ただ、この本が環境問題に関心をもつ人びとやメデイアにも好意的に受け入れられた最大の理由は、やはりダイオキシンに関する情報がきちっと紹介されていたからだろう。「ダイオキシンが心配ないなんて、とうてい信じられない」とかたく信じる人々に、とにかく理解できるように努力したという渡辺氏の言葉どおり、具体的な数字をたよりに懇切丁寧に説明がされている。「サリンの二倍!」に象徴されるようなダイオキシン禍がいかにうそまやかしであったか、それこそ素人にも十分理解できる書き方になっているのだ。
ダイオキシン騒動についての渡辺正氏の見解をインタビューと著書からまとめてみよう。
・私たちが摂取するダイオキシン類の95%は食品からくるもの。ダイオキシンに弱いモルモットのデータをヒトにあてはめてみると人生10回分(820年)ほどの食事を「イッキ食い」しない限り、ダイオキシンが半数致死量に達することはない。そんなことは現実にありえないので、急性毒性を問題にするのは見当違い。「サリンの2倍、青酸カリの1000倍」は的外れな脅し文句。
・日本の環境を汚染するダイオキシンの大半は、過去の農薬が原因。ダイオキシンを問題にするなら残留農薬を問題にすべきで、焼却炉や塩素系プラスチック悪玉説はまったくの見当違い。
・環境ホルモン作用のような慢性毒性説も間違い。ここ30年ほどヒトのダイオキシン摂取量も体内濃度も減少している。昨今「増えてきた疾患」の原因とは考えられない。そもそもダイオキシンはがんを促進させる作用はあっても単独でがん細胞を芽生えさせる発がん物質ではない。それどころか、「制がん作用」があるという研究すらある。
・ダイオキシンは、ngやpgといった大変小さな重さの単位を使う。こうした単位の物質を検出し測定できるようになったのはひとえに感度の高い分析装置ができたことによるもの。その意味でダイオキシン問題とは、先端分析技術が産み落とした鬼っ子であるともいえる。
・以上のことから、ダイオキシンは普通の暮らしをしている限り何も心配ない。知恵や金をもっとリスクの高い発がん物質やクルマの排ガスの研究にあてるべきである。
・意味のないダイオキシン法を見直し、望むらくは廃止すべきである。
渡辺氏は、ダイオキシンの専門家ではない。しかし、専門家でないからこそダイオキシンの問題のおかしさを指摘できたという。専門家は本当のことをわかっていたとしても、それを言うことができなかったのではないかと言うのだ。そこには環境問題特有の力学が働いているという。
「大物の研究者は前言を翻したくないし、メディアも撤回したがらなくて、違うとわかったら黙ってしまうだけ」。また、行政側からすると、環境ホルモンにしろダイオキシンにしろ、新しい仕事と捉えている。そうすると新しい組織を作り、新しい名目で予算を取り分配することになる。役人の仕事は、どれだけの予算の仕事を動かすかで業績を評価されるから。そういう力学の中から出てきたのが今回の「ダイオキシン騒動」だったと渡辺氏は指摘する。メディアやテレビ報道が煽りたてたとしてマスコミの責任だと批判する人も多いが、科学者自身の責任も免れないというのである。
「研究者がまず言うべきは、その数字が基準値に対してどのくらいなのかということ。安全係数をかけた数字なので基準値というのは好きではないが、やはり、危ないかどうかという判断ができる材料を一緒に提供しないと、普通の人は絶対にわからない」。
ngやpgという単位がどのくらいの数値なのか、それを伝えるのはメディアというよりは、科学者自身ではないか。その数値の意味を正確に知っているのは、ほかならぬ科学者たちだからだ。もとより、このことは環境問題に限ったことではないだろう。科学者が市民に対して、事実だけでなくそのもつ意味や背景を正確に伝えること。それは、今日の科学報道のすべてに言えることだろう。科学者のマインドが問われているのである。
「リスク・ゼロ」はありえない
さて、渡辺氏の発言でもう一つ印象に残った言葉がある。「リスク・ゼロなどありえない」という発言だ。「危険なものは絶対にない」というわけには土台いかないのである。そもそも「絶対」というものがない。そういう気持ちを日頃から私たちはもっていないといけないという指摘である。「リスクは可能な限り避けたいが、ゼロにはならない」ということは、リスク論ではしばしば問題になることである。リスクという概念には単なる危険を意味するだけではなく、危険を前提としたうえでそれをいかに軽減するかという危険への対応も含意されている(『リスク学辞典』参照)。「リスク・ゼロなどありえない」という感性をもつということは、考えてみれば当たり前のことだろう。だが、そうだとすれば、私たちは常になんらかの危険にさらされているということにもなる。それがどんなにささいなことであっても、それがリスクだといえばリスクになる。確かに「いくらなんでもそんなことはないだろう」と思われることが、現に次々に起こっている。超高層ビルが旅客機に直撃されるということも、幼児が12歳の少年にビルから突き落とされることも、普段なんの疑いもなく飲んでいた牛乳で食中毒を起すことも、どれもこれもリスクである。しかも、今ではそのリスクに遭う確率までしっかり表示されていたりするのである。すべって転んで死ぬ確率は3万分の1だとか、仕事で死ぬ危険は100人に1人だとか、ネットがらみで犯罪に遭う確率は10万分の1だとか、ただ寝ているだけでさえ650分の1の確率でなんらかの事故に遭うというように(内藤誼人著『ここにいてはいけない』)。
リスクは結局のところ確率にすぎない。それが自発的な行為によってもたらされることだろうと、いわゆる自然災害といわれるものや予期せぬ事故だろうと、しょせんは確率なのだ。注意しようがしまいが、遭うときには遭う。こうして普通に生きているということ自体が、ある意味では何分の1かのリスクをかいくぐってきた結果にすぎない。こうした見方を推し進めると、人生そのものがすでに偶然性の所産だということにもなる。「リスク・ゼロ」ではないということは、極論すれば自分というものの存在自体が偶然的なものにすぎないことを認識することでもある。
こうしたリスク論の拡張は、ばかげた考えのように聞こえるだろうか。それがばかげているというのならば、たとえば、自然災害と人為的な事故の違いを明確に言えなければならない。ここからは自然災害、ここからは人間が関与した事故というように。しかし、そんな区分けは現実的には無理だろう。
「リスク・ゼロ」でないならば、すべてにリスクが免れないと仮定して、リスクがあるかないかを評価するような軸が必要である。そういうことを議論できるような、旧来の枠を超えた新たな視点が必要になってくるということなのだ。
公共的「知」をどうつくるか
松本三和夫氏が「構造災」という言葉をつくったのは、まさしく今言ったような新たな視点を導入するためであった。「リスク・ゼロ」がありえない現状では、天災か人災かというような分け方はできない。言い換えれば、天と人の間の社会構造、その仕組みから起こる災害の方が圧倒的に多いのである。そうした「構造災」を前にした時、これまでのような「知」で対応することは難しい。つまり、こちら側の「知」のあり方もつくり変える必要がある。「もっと広い意味での知性、知恵やある種の良識や暗黙知も含めたような知のあり方」が求められてくるというのである。「構造災」としかいいようのない事故が発生した場面では、それを科学や技術による失敗にしたり、市場の失敗にしたり、あるいは政府の施策の失敗として片づけてしまうことはできない。そのように失敗を一元化してしまったら、「構造災」という現代の災害の本質はますます見えにくくなってしまう。そこで、暗黙知を含めたこれまでの知性がうまく作動しなくなったことを、「知の失敗」として捉え直そうというのである。
問題は、科学技術を支えている「知」のあり方にあるのだ。松本氏の議論を整理しよう。
科学技術の社会問題というのは、科学技術に直接関与していない万人に影響を及ぼす。いわゆる公共の問題として取り組まないと、いつまでも同じ型の問題「知の失敗」が繰り返されることになる。科学、技術、社会のインターフェイスの構造を変えていかなければならない。
ところで、巨大技術というのは、いったんある軌道を走り始めると方向転換がしにくい「経路依存性」をもっている。そこで常にその問題に対して自己言及できる仕組みが必要になってくる。一方、科学技術や社会にはそれぞれ虚と実の面があるが、科学技術、社会共々お互いの虚と実を把握しきっていない。そのために同じ型の問題を再生産してしまう。その構造を螺旋構造としてモデル化すると、科学技術と社会の界面には必ず盲点があり、そこから問題が発生することがわかる。このモデルは、また、従来の成功/失敗の二分法に対して、成功/失敗を一種の傾きとして見る見方を提起する。
真の問題は「社会」の定義にあるのではないか。「民意」とか「社会の総意」とか言われる時の「社会」のイメージとは何か。科学技術は「社会」をどう見ているかがいちばんの問題だ。社会は一枚岩ではない。社会は、多様な行為者間の複雑なダイナミズムによって形成されている。それをどう見るかである。松本氏は、社会を官、産、学、民の四つのセクターに類型化し、それを軸に捉え直そうと提案する。この視点は公共性の概念にも更新を迫ることになる。公共性をどのセクターにも担保できるようにするためである。
おそらく、松本氏がここでいうセクター論が「知の失敗」を回避する新たな「知」なのだろう。この新たな「知」の特徴は「知の失敗」の「知」と、ではどこが違うのか。筆者は次のように解釈する。
これまでの科学、技術(伝統的)は実証主義に重きを置き、真偽を明らかにすることを目的としてきた。たとえば、発見、発明の何が成功で何が失敗かを見きわめる判断も科学、技術が担ってきた。それが可能なのはその対象がすでに「終わっている」科学や技術だからだ。最終結果が明らかになっているものに対しては、科学、技術は評価を下すことができる。しかし、先ほどの螺旋モデルが対象とするような、現在動いている「進行中」の科学は、正しいか正しくないかという判断すら難しい。成功/失敗の傾きが次々に変化する状態である。そういうダイナミックに変化し続ける科学、技術に対して、旧来の科学、技術の評価基準(静態的な)を採用することはできない。それを無理に使用すると「知の失敗」が発生する。「活動中の科学」(science
in action/B.Latour)には、新しい「知」としての科学、技術の評価(動態的な)が必要になる。こうした構造的な変化=知の地殻変動を理解する方法として、たとえば、言語学に登場したパフォーマティヴィティの理論が参考になると筆者は考える。
言語には、ものごとの状態や事実を記述する役割だけではなく、その言語が発せられたことによって発話者自身がある行為を行うという役割ももっている。それをコンスタティヴ(事実確認的)な言語に対して、パフォーマティヴ(行為遂行的)な言語と呼んでいる。パフォーマティヴィティへの展開は、人間の言語活動を考える時に、事実を確認するために言語を使うことと同じくらい、いやむしろそれ以上に行為遂行的な使用の方が多いという現状があったからだ。つまり、生きた言語を研究するためには、生きた言語学が必須だったのである。いったん生きた言語に視点を向けると、言語だけを対象にするわけにはいかなくなる。それを使用する人間や人間の集団としての社会、そこで交わされるコミュニケーションさえもその対象になる。パフォーマティヴィティへとシフトした結果、言語学は言語学という閉じた領域から必然的にその外部へ自らの領域を広げざるをえなくなったのである。言語学はパフォーマティヴィティへとシフトすることで言語学という枠そのものを拡張したのである(このあたりの事情については『談』no.62「パフォーマティヴィティの言語へ」参照)。
松本氏のセクター論を活かすためには、科学、技術を評価し(評価される)「社会」を再定義する必要がある。それは、言語学の展開が示したのと同じ理由による。知が扱う科学、技術は、まさに「進行中」、「活動中」の科学、技術だからだ。科学、技術、社会は、いまや一つのシステムを形成している。三者は、互いに影響しあいながら活動し発展する。「知の失敗」、そしてそれを回避するような新たな「知」も、この拡張された社会システムの関係から発生するのである。
「安全」をとるか「安心」をとるか
柘植あづみ氏は、インタビューの冒頭イヌイットの人たちの出産の話を紹介した。要約してみよう。
カナダの州政府がイヌイットの人たちの妊産婦死亡率と乳幼児死亡率を下げるために、それまでコミュニティの中で行われていたお産を、都市の大病院で出産するように推進していった。設備の整った病院での出産はさぞかし彼女たちを喜ばせただろうと医療者側も州政府も思っていたのだが、反応は意外なものだった。イヌイットの女性たちは、こんな不安で嫌な体験はもうこりごりだというのである。コミュニティでの出産には、(設備こそ粗末かもしれないが)家族や近所の人びとがみんな集まってきてくれる。みんなが出産の無事を祈ってくれる中で子どもを産むことができた。ところが、病院での出産は、医療関係者が立ち会うだけで、産まれてしまえば(子供と二人だけで)病院に残され、それも24時間後には退院させられてしまう。こんな出産のどこが安心なのかというのが彼女たちの感想だったのだ。
医療者や科学者側の考える「安心」と、患者や消費者側の感じる「安心」には、大きな認識のズレがある。医者は、「安全」であることが患者に心地よさや安心感をもたらすと考える。ところが、患者が求めていたのは、そうした「安全」への配慮よりも「安心」感であった。「安全」よりも「安心」。「安全」はリスクの問題だが、「安心」はこころの問題。ここに埋めがたいズレが生じているというのである。
この「安全」か「安心」かという認識の違いは、従来の科学者/一般人という図式の欠陥を埋めるような視点を提供してくれるように思われる。一方に知識があって他方に知識がないといった、いわゆる「欠如モデル」に代表される専門家/非専門家、プロ/素人の関係は、知識のあるなしが問題で、知識が増えればその差は埋められると単純に考える。つまり、両者を分けるのは知識の量であるというわけだ。
しかし、「安全」か「安心」かという認識の違いは、そうした知識量とはまったく異なることを起因としている。たとえば、医者が「安全」の理由をどんなに並べたところで、患者の「安心」感は得られないだろう。そもそも求められているものが異なるのだ。イヌイットの女性が出産時に最も必要としていたのは、清潔な環境や緊急時の備えでも、いわんや正確な分娩技術でもなかった。彼女らは、そこで出産を見守ってくれる、共に祝ってくれるそういう人々の感情、愛情が欲しかったのである。こう言うといかにも陳腐に聞こえるかもしれない。しかし、よくよく考えてみると、ここには本質的な問題が横たわっていることに気づく。
彼女らが出産の場面で欲しかったものは「安全」といういわゆる「セキュリティ」ではない。「安心」というある意味ではセキュリティとは無縁の、場合によってはなんの保証にもならない単なる「気持ち」であった。これは何を意味しているのか。出産は女性にとって大きなリスクである。場合によっては死ぬこともあるし、また生まれてくる赤ちゃんにも同様のリスクはある。しかし、彼女らは、そうしたリスクを軽減するはずの病院よりも自分たちの暮らすコミュニティでの出産をより強く望んだ。リスクがあるかないかは、その場面で見る限り、あまり重要なファクターではない。それよりもメンタルな部分での「安心」を望むのである。医療者側はしきりにアカウンタビリティを強調するだろう。医者も一人の人間であるのだから、患者の立場に立つことはできるし、その立場から患者に接することはできる。だが、柘植氏も述べているように、患者の立場で話を始めた時にも、医者は医者であることをやめることはできない。患者と同じ視線でものを見れば、医者も患者の求めているものがわかると良く言われるが、そういう視点で見られるようになったとしても、医療という「めがね」をはずすことはできないのである。その「めがね」を外したら、その時から医者は医者でなくなる。当たり前のことだ。
ちょうどこれとまったく同じことが不妊治療という場面でも起こっている。柘植氏は言う。「医者の意図とは別に、医者は選択肢を提示しているつもりでも、受け取る側が医者が説明するという行為にメッセージを読み取ろうとする」。しかし、これは選択肢とはいえないだろう。「〈検査は安心をもたらす〉と言われる。ほとんどの人が検査で何の異常も見つからずに、出産も無事にすんでいくから。それは嘘ではない。だが、残りの1割、もしくは1%の人たちが、その結果に混乱し、〈私はどうしたらいいんだろう。家族に相談しても、どうしていいかわからない〉という状態になった。そういう人たちの不安をかえって高めてしまったことに、医療者なりほかの99%の人たちが、どういうふうに想像力を働かせることができるのか」。多分、できないだろう。そして、99%の無事にすんだ人びとにとっても。つまり、ここで言われる「安心」は、リスクにかかわるものだからだ。「安心」をもたらすとはいえ、リスク・ゼロはありえない。そうであれば、確率的に安全か安全じゃないかということ以外の意味はない。そのリスクをより少なく見積もるか多く見積もるか、その選択をするのはほかでもない出産を控えた女性だ。より正確に言えば、他に還元できないその一人の「女性」なのである。だから、その一人の「女性」に医者が意思決定の材料として医学的知識を提供したところで、ほとんど意味がない。それどころか、そうした知識は、ますますその一人の「女性」の選択を困難にさせ、かえって「不安」にさせるだけなのだ。
イヌイットの女性に与えようとした「安全」は、言うまでもなくこの場面で言えば医学的知識と同類のものである。イヌイットの女性はそれを拒否した。しかし、今まさに出生前検査を受けようか迷っているその一人の「女性」は、それを拒否できるだろうか。おそらくできないだろう。なぜならば、リスクを回避するかもしれないという意味での「安全」への期待があるからだ。つまり、ここでは、感情や愛情としての「安心」よりも、リスクを見積もることのできる「安全」が求められている。イヌイットの出産と一見似たような状況にありながら、そこから導き出される解は、まったく逆なのである。
いずれにしても、こうした選択に、結局のところ科学はほとんど貢献していない。その選択決定に影響力をもっているのは、文化や価値観である。「それは自然だ」という認識においてさえも、人々は科学よりも文化や共同体が共有するような価値観で捉える。社会の支配力の方がはるかに強いのである。
科学にわからないこと、科学だからわからないこと
「アインシュタインが、確率でしか電子の挙動が予言できない量子論を批判して、〈神はサイコロ遊びをしない〉と述べた。量子論も実験を通じて検証するしかないが、すべての実験を行うことが不可能な以上、その理論の真偽を決める完全な証明は不可能。そこでアインシュタインはどうしたか、神に仮託してそれを拒んだ。それに対して、ボーアは〈なぜ、神の意図がわかるのか?〉と反論し、微視的世界は確率論的な理論で過不足なく説明できるのだから、サイコロ遊びが好きな神を受け入れればいいと言った。どちらも、それぞれ自分に都合のよい神のイメージを抱いて」いるのである。うまくいけばいったで神をもち出し、それがまだ未知であれば、またそこに神を見る。審美観における神と、証明できない「なぜ」における神。結局のところ、物理学者は神を葬るどころか、神と付かず離れずして一緒に科学を発展させてきたのだ。そして、今や、その神は、八百万の神よろしく、変幻自在に姿形を変えることのできる存在になった。つまり、現代の神は、「なんでもあり(anything
goes)」の神なのである。
もっともここで言う神は、あくまでも人間がつくった神である。いわば観念としての神である。だからこそ、なんにでも変わることができるし、人間の方が変われば、それと一緒に神も変わると池内了氏は言う。「科学者はなんでも知ってるという〈人間原理〉こそ、科学者の傲慢であり」、それを主張したい科学者が少なくないのも事実。しかし、現に科学はいまだ解明されていないものを五万ともっている。まだまだわからないことだらけである。であれば、「そのわからないことを神と考えても、いっこうにかまわないのではないか」と池内氏は言う。なぜならば、それは観念なのだから。要するに、それは「あたま」の中から生まれ「あたま」の中にあるものだからだ。ある法則が発見されたとしても、それがなぜそうなっているのかということについては、じつは科学は何も答えていない。ただ「そうなっている」と言っているにすぎない。
池内氏の冒頭の発言は、大森荘蔵氏が言う「重ね描き」と同じことを言っているのだろう(editor's note before参照)。私たちは、なまの世界を前にして、それを科学的発見という言葉で言い換えているにすぎないのである。だからこそ、そこに神が現れる。なまの世界、なまの経験とは、今自分が生きて感じているそのすべてのことである。今自分が生きていて感じていること、大森荘蔵氏流に言えば、まさしくそれが観念である。つまり、「あたま」の中で起こっていること、感じていること。もとより、ここで言う「あたま」は、脳内の情報処理機能のことを言っているのではない。ふだん「こころ」と呼んでいるようなもの。そうした「こころ」が感じていること、「こころ」の働きを、ここでは観念と表している。
科学者といえども科学から神を追放することができなかったのは、それが「重ね描き」にすぎないということを科学者自身が薄々わかっていたからではなかろうか。科学的発見が科学者の「あたま」に宿った時のことを、科学者は「Ahaの瞬間」と呼ぶ。まさに、それは天から降りてくるような感じだと科学者たちは言う(「Ahaの瞬間」『AI
ジャーナル』)。科学者はその瞬間、その発見を観念として認知し、それを神と呼ぶのである。しかし、その科学にもついに「わからないこと」があるということがわかる瞬間がやってきた。観念という神もついに自らを放擲せざるをえない発見。それがゲーデルの「不完全性定理」であった。神は、この発見によって、神自身が神であることを放棄したのである。言い換えれば、観念はこの時から、「なんでもあり」の観念になったのである。
それでもなお「科学を選ぶ」意味とは何か
高橋昌一郎氏は、昨今の科学離れよりも、科学嫌いが増えていることが不思議でしょうがなかったと言う。そして、その謎を探りながら、科学が失いかけていたものが哲学であり、科学における哲学の復興を訴えた。著書『科学哲学のすすめ』は、その意味であとがきにあるように、科学を社会学的に考察しようというものではなく、あくまでも科学における哲学的思考の復権にアクセントを置いている。最後に高橋氏をお尋ねした理由もそこにあった。科学と社会の界面を考察してきたが、じつは科学の内部にその争点があるということが見えてきたからである。つまり、科学自体が、これまでのような姿形をしていないとしたら、それは科学にとってどのような事情によるものなのか。あるいは、神としての科学がついにそれを放棄してしまったという事実をどう理解すべきなのか。それは、社会の問題である以上に、科学自身の問題である。私たちが考察しなければならないのは、科学そのものではないかと考えたからである。
「今日いわゆる文化人を見渡してみると、大多数が何らかの意味で〈反科学〉を主張しているのではないかと思える。なぜこれほどまでに科学は嫌われるのか」。「原子力開発や遺伝子工学の廃止を求め、臓器移植や動物実験の禁止を訴え、西洋医学や精神医学に不信感をもち、有機栽培や自然食品を好み、環境保護運動やフェミニズム運動に賛同し、ヨガや気功を実践し、超自然現象や神秘主義に憧れ、星占いや宗教に基盤を置いて生活をしている人……。実際に周囲を見渡してみると、少なくとも部分的にこのような傾向をもつ〈文化人」〉あるいは〈知識人〉は少なくない」。
こういう傾向が強く見られるのは、科学的知識がないからというわけでもなさそうだ。むしろ、科学的教養をもつがゆえに、反科学を標榜する知識人は多いのである。それはなぜだろうか。科学が神であることを放棄したことも、そうした潮流をつくりだした原因の一つだと思われる。神自身がそれまでの神の座を降りてしまったのだ。池内氏が言うギャンブルにうつつを抜かす神の登場である。もはや、科学は万能の知を主張することができなくなった。知が知でなくなったのである。その歴史的な事件の首謀者こそクルト・ゲーデルそのひとであった。
ゲーデルの「不完全性定理」の発見は、科学を科学としてあらしめる根拠を科学そのものから奪い取ってしまったのである。科学は「不完全性定理」の発見によって、その存在理由を失ったのだ。「科学を厳密に表現しようとすると、数学を使わなければならない」が、「じつは数学というシステムの中にも〈不完全性〉があることがわかっ」たのである。しかも、「ゲーデルが導いた〈不完全性定理〉は、(科学を最も根本のところで基礎付ける)数学の世界においても、〈真理〉と〈証明〉が完全には一致しないという結論を示してしまった。しかも、それだけでは終わらない。ゲーデルは、一般の数学システムSに対して、真であるにもかかわらずそのシステム内部では証明できない命題Gを、Sの内部に構成する方法を示し」てしまった。つまり、「不完全性定理」は、論理的に完全なシステムはこの世界に存在しないことを判明してしまったのである。理性主義の象徴としての科学は、この時点で崩壊した。ファイヤアーベントがいみじくも言ったように、私たちの進むべき道はアナーキズムしかないのだろうか。「なんでもあり」という、その意味ではあらゆる考えが相対的な価値しかもたない、反科学でさえもが科学と正当に対峙しうる世界。じつは、現代とは、すでに科学を必要としない社会になりつつあるのかもしれない。
私たちは、本当に科学を必要としないのだろうか。反科学は本当に科学を葬り去ってしまったのだろうか……。
いや、だからこそ、今、科学をもう一度議論の俎上に登らせようと高橋氏は提言する。まず、その手始めにとにかく議論をすることだと言う。それも哲学的な議論でなければならない。「今、科学はどうなっているのか、科学にどういう意味があるのか、科学とはわれわれに何をもたらすのか、科学者にこそ科学哲学の議論をしてほしい」。要するに「もっと議論を」である。
「科学も反科学も非科学も含めて、自分以外の人々の考え方や生き方をどのように理解するのかということ」。「大切なのは、意見が違うという結論ではなくて、なぜ意見が違ってくるのか、その理由を議論することだと」思う。そして、何よりも「なぜ科学を選ぶべきなのか」を問い続けること、それが科学哲学であり、現代のわれわれに最も必要なことではなかろうか。
科学技術の進展は、やがて人々から科学(的思考)の必要性を失わせることになるという(Shamos,Morris H."The Myth of Scientific
Literacy")。テレビであれ携帯電話であれ、またコンピュータでさえも私たちはその仕組み、システムを知らなくても使いこなすことができる。その仕組みやシステムを考えなくても、それらは使われることによって私たちにベネフィットを提供する。科学(的思考)は、そうした技術および技術の産物にとってはむしろじゃまである。観念である科学は、十分にいきわたった時、観念であることを忘れさせるだろう。今日、科学は、私たちにとって思考の対象でも、思考の道具でもない。思考の結果ですらないかもしれない。そのような科学が失効した時代に、それでもなお「科学を選ぶ」としたら、それはどのような動機によるものなのか。そして、そこにどんな意味があるのだろうか。科学哲学が深刻に問われなければならない理由は、まさにその問いの中にある。科学とは何かと問うこと。それは、科学を放棄した後にいまだに残る観念、つまり、自分自身の、自分の「あたま」の中にある「知」を問い直すことなのではなかろうか。
(佐藤真)
|