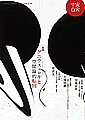![editor's note[before]](../no75/img/editor_before.gif)
空間論的転回再考
都市への視線、「空間」という問題構制
「建築とは凍れる音楽」だと評したのは文豪ゲーテでした。このゲーテの言葉を借用して、「都市とは凍れる現実」ではないかと言ったことがあります。凍りついた、すなわち静止した音楽が具体的な音を発しないのと同じ理由で、静止した都市からは、本当の都市の姿、生き生きとした音=「現実」は聞こえてこない(見えてこない)からです。
都市の専門家たちは、これまで凍りついた現実こそが都市であるかのように語り続けてきました。凍りついた現実とは、都市を構成するさまざまな要素のこと(もの)です。建築や土木構築物、道路や街割、制度や法律が都市を形づくるものであることは間違いないけれども、それは都市を都市たらしめているものの一部です。こう言ってよければその都市の形象にすぎません。都市の専門家たちによって捉えられた都市とは、その意味で常に/すでに過去(形)の都市なのです。
むろん、ゲーテは、建築の内部に「真善美」が凍結されていることを示そうとしたわけで、建築をむしろ讃える意味でeine erstarrte Musik(≒frozen music)という言葉を使ったのでしょう。都市の専門家たちにとっても事情は同じ。凍結された都市こそが彼らにとっての都市なのです。
都市の美も用もあるいは真実も凍っているから見えるわけで、解凍を始めればそれらは雲散霧消してしまう。都市は単なる社会になり、生活圏になり、人々が集い活動する場になります。都市の専門家は、解凍された瞬間から、その場所へのアクセスを失ってしまう。
だが、私たちにとって、都市とは紛れもなく生ける現実です。言うまでもなく、その現実とは社会のことであり、生活圏のことであり、活動する場のことです。私たちの生きる都市は、一度も凍ることなくただ流動し続ける現実そのものなのです。フローであり、フローと「いま・ここ」でリアルタイムにアクセスし続けるそのこと自体が都市とのかかわりであり、そのまるごとの現実をとりあえず都市と呼ぶ。少なくとも私たちにとっては、そこにある現実こそが都市なのです。
歴史や事物を閉じこめた氷としての都市、一方、凍結することなく絶えず変化し続ける現実としての都市。この都市に対する二つの見方は、一見水と油のごとく対立しているように見えます。事実、一九七〇年代以降登場してきた非専門家たちによる都市論の多くは解凍した後の、あるいは一度も凍ることのない現実としての都市をその対象としてきました。記号論、身体論、社会構築論、システム論、消費社会論といった立場から盛んに都市は語られてきましたが、そのほとんどが後者の立場からだったことは偶然ではありません。
両者は棲み分けながらそれぞれの道を切り開いていくなか、一九九〇年代を前後する時期に、新たな胎動が起こります。後に「空間論的転回(spatial turn)」と呼ばれることになる都市論の新しい展開です。
これまで「空間」を扱う学問分野は、空間の科学を標榜する地理学でしたが、都市社会学や文化人類学、カルチュラル・スタディーズなどの隣接する諸科学の影響を受けて、改めて「空間」それ自体を問題構制の基礎に据える考えが地理学のなかに浮上してきました。とりわけ「建築学・都市計画といった広範な人文・社会諸科学での都市論・都市研究の展開において、〈空間〉がそれぞれの分野の枠組みを超えて焦点を結ぶ知のトポスになった」(「はじめに」『都市空間の地理学』より)というのです。つまり、今の文脈で言うと、後者の立場から前者も巻き込む形が生じ、その両立場を通底しながら発展していくのが「空間論的転回」でした。
この新しい動向は、繰り返すまでもなく「空間」に定位し、「空間」をめぐる問いであることに特徴があるわけですが、なぜそれが「空間」であったのか。それは、「〈空間(化された)表象〉が、都市社会を構制する諸力(資本・権力・文化・イデオロギーなど)を分析し読み解く際に、きわめて有効な概念・装置として認識されたからにほかならな」(同上)いからです。たとえば、従来空間というと主に数学や哲学の対象でした。デカルトの均質空間とかニュートンの絶対空間、あるいはカントの認識の先験的形式としての空間など、そこで扱われる空間は、社会的現実から遊離した、いわば心的空間として捉えられるものでした。xyz軸からなる無味乾燥の空間。重量ゼロの純粋空間が、それまでの私たちの認識する空間だったのです。
それに対してフランスの思想家アンリ・ルフェーヴルは、そうした従来の空間概念を射程に、空間が内包する問題系を掘り起こしたのです。私たちの思考を基礎付ける「観念的」空間と「現実の」空間を隔てている距離こそが問題ではないかと切り出した。つまり、「空間を主観的形式にも客観的秩序にも還元せず、社会的に構成されたものとして捉え直」(「思想家アンリ・ルフェーヴル 空間論とその前後」同上)そうとしたのです。言い換えれば、旧来の空間概念の自明性を問題視したのです。
この空間の自明性への疑義は、かえって人々の空間への関心を呼び覚ましました。ルフェーヴルは「空間は社会的に生産される」というメッセージを残します。「空間論的転回」は、まさにこのメッセージに促されるように、地理学のみならず、広く都市を対象とするさまざまな学問領域へ波及することになります。そして、その空間の考察は、空間の編制と言説の交錯する場所、すなわち都市へと向かいます。今号は、この地理学の周辺で起こった「空間論的転回」を手掛かりに、私たちの生ける現実、都市について考えてみようと思います。
都市の理想と現実
人間のいない「都市」は、果たして都市といえるのでしょうか。いわゆる都市の専門家である都市計画家、建築家がこれまで描いてきた都市像のなかには、現実に生きる人間を想定していないのではないかと疑いたくなるものがありました。とりわけ近代の都市計画には、そうした人間不在の都市プランが少なからずあったように思われます。都市の理想……緑、太陽、空間の重視……を優先するあまり、肝心の人間の存在が不当に小さく見積もられていたからです。
都市の理想を掲げ、その実行こそが都市計画の本義であると高らかに宣言したのがシアム(CIAM)でした。シアムとは、ル・コルビュジエやヴァルター・グロピウスという建築家、デザイナーを中心とするグループで、「都市」形態の理想主義を世界に啓蒙し、とくに戦後の復興計画には絶大な影響力をもちました。
しかし、シアムの主張する理想主義にはそもそもムリがありました。理想解を具現化するにあたり、その遂行の妨げとなる予測不可能な因子は、最初から捨象される傾向があったからです。予想不可能な因子、とりわけ「人間」はその最たるものでした。そうした理想主義の下、人間の行動形態は可能な限り単純化され、数量化の下一元化されます。その結果、理想解を手に入れるのと引き換えに、不確定因子としての人間の存在意義は、極端なまでに縮小化されてしまったのです。
一九三四年に活動を開始したシアムは、早くも五〇年代半ばを過ぎた頃から、こうした理想主義の限界を露呈させることになります。まず、人口の増加があります。人口の増加は、きわめてプリミティブな形で不確定因子の存在を主張することになります。さらには行動形態の多様性が主張されるようになると、機械論的に一元化された枠組み自体が崩れ始めます。その構成因子たる人間の存在を最小化することで都市の理想を実現しようと企てたわけですが、その人間が、最小化どころか最も大きな変数となって立ち現れてきたのです。
理想としての都市、その欺瞞性が一気に吹き出してきたのは、わが国の場合六〇年代でした。理想主義に懐疑的な急先鋒が、まず同業の建築家たちから出てきました。
「シアムの時代の都市のイメージというものは、巨大都市つまりメトロポリスのイメージであって、技術革新の力で拡大した領域の問題を構想するという形で、その中の人間の、都市生活の構造というものについては本質的な変化はない、というとらえかたであった。ところが、シアムには成長概念がないというのがぼくらの批判である。たとえば、シアムがつくったブラジリアとかシャンデガールという都市計画をみると、固定化されたパターンでもってとらえられていて、その都市が人口の増加や生活構造の変化などにどのように対応するか、その方法論が皆無である」(黒川紀章「未来は突然にやってくるか?」一九六七年)
今から四○年ほど前に、当時新進の建築家であった黒川紀章は、建築と連関する都市計画に対して大胆な批判を試みました。黒川の指摘は、都市計画というものが技術的な問題をはらんでいるというのではなく、流動的な生活構造に対応できていないと指摘したのです。黒川は、六〇年代にすでに都市計画というものの本質的な矛盾を見て取ったのです。都市計画は、人間の扱い方を見誤っていると。より正確に言えば、そこには人間がいない、というのが黒川の主張でした。
都市に主体性を組み込む
シアムの中心理論にはもう一つ大きな概念として「コミュニティ」がありました。都市を構成する単位のことで、ここでも人間はきわめて抽象的な存在として扱われ、都市という形式的な枠組みの内部に制度化されるものとして位置付けられていました。黒川は、このコミュニティという概念にも冷や水を浴びせます。人間はすでにコミュニティをはずれたところで生活し始めている。コミュニティそのものが流動化しているとはいえないか。そうした都市の内部に起こっているゆらぎをいかに方法論化するかが都市の当面の課題である、と黒川は主張したのです。そこで黒川がもち出してきたのが主体という概念でした。すなわち、人間の主体性こそ都市にとって最も必要なものではないかと提起したのです。。
人間は決して予定調和的な行動をしない。不確定な行動をするのが人間であり、そうであればこそこの不確定性を都市という現状にあらかじめビルトインしなければならないであろう。動かないものとしてのインフラストラクチャーに対して、動くもの、つまり不確定要素としての人間の主体性を組み込む。言い換えれば、不動のものに随時交換可能な仮説部分を接合していく。後に黒川が提唱した「メタボリズム(という建築家グループ)」のコンセプトはこの考えに基づくものでした。
建築の可能態として都市を構想したことは、少なくとも理想形態として抽象化された都市というものをより現実に引き戻したという意味で、シアムの欠陥を補うに十分なものだったという評価は妥当でしょう。ただ、黒川の思想の基盤には、都市に対する建築の優位が暗黙の前提としてあったことは否めません。仮に都市に主体性を回復させようというのであれば、建築もまたその障害になります。建築も同様に都市の構造物であれば、代謝機能(メタボリズム)を妨げるものとして都市の前景に出てくるものだからです。事実、黒川もそれを認めていて、建築さえも二次的な形態として背後に隠れ、むしろ前景に偶有的な人間の生活の原形を置くようなイメージをもっていたようです。そして、そのヒントをハプニングに見出そうとしたのでした。
ハプニング、今ではまったく聞かれなくなった言葉ですが、偶発的なインタラクションを重視する表現行為のことで、今風に言えばパフォーマンスに近い。主に身体を媒介にして、都市そのものとかかわろうとするハプニングは、静態的で機械論的な都市機能に内部から揺さぶりをかける「主体的な行為」としてみなされたのです。身体を使用して街頭へ飛び出していく。黒川にとってハプニングは、都市から捨象された人間をあらためて都市に呼び込むための手段として称揚されたのです。それは、別の言い方をすれば、人間の見えない都市に対する人間の回復でもありました。
黒川の「都市に主体性を」というスローガンは、こうして都市における人間の再生へと結実していきます。それは言い換えれば、近代都市が、都市の現実と向き合うことによって、生きる人間の空間として再定義されたことを意味します。都市は、人々が生活する具体的な場であり、文字どおり生きる場所として自覚されたのです。われわれ人間が拠って立つ場所であり、きわめて具体的な物理的空間としての領有。都市はこうして、その内部に人間存在を抱えながら、常に変化するgroundとして自覚されることになったのです。
ゲニウス・ロキの地理学
都市は人間のいる場所であるというきわめて当たり前の事実を、わざわざ確認せざるを得ない状況が、じつはわが国ではその後もしばらく続くことになります。黒川が都市に主体を見出してから二〇年以上経ってからも、東京という都市は相変わらず人間不在のまま都市再開発に明け暮れていました。バブル景気がピークに達する八〇年代、都市改造の槌音はいよいよ強くなり、激しさを増していきました。場所を構制する諸力を分析し読み解くには、八〇年代の東京こそ最もふさわしい場所になるとはいかにも皮肉な事態です。きわめてアイロニカルな形で人の見えない都市を、東京はその後も日々更新し続けていたのです。
いまだ空間論的転回を経ていないこの時期に、都市史の分野から卓抜した都市研究が出ました。『東京の<
地 霊
>』と題されたその研究は、いわゆる人文・社会学系の都市論とは明らかに一線を画するものでした。
「(…)都市史研究といわれるものの大半が、じつは都市そのものの歴史ではなく、都市に関する制度の歴史であったり、都市計画やそのヴィジョンの歴史であったりすることに、かねがね私は飽き足らなさを感じていた。都市とは、為政者や権力者たちの構想によって作られたり、有能な専門家たちによる都市計画によって作られたりするだけではない存在なのだ。現実に都市に暮らし、都市の一部分を所有する人たちが、さまざまな可能性を求めて行動する行為の集積として、われわれの都市はつくられてゆくのである」
著者の鈴木博之はそう語り、自らの研究が狭義の都市論ではなく、その拠って立つgroundをも視野に入れた土地論であることを表明したのです。
「民間活力の導入、国鉄分割民営化など、国土をめぐる新しいうごきが一九八〇年代なかばの中曽根政権下での政策から活発になった。とりわけ東京の土地は、いままさに未曾有の変貌をとげつつある」とし、「どのような土地であれ、土地には固有の可能性が秘められている。その可能性の軌跡が現在の土地の姿をつくり出し、都市をつくり出してゆく」。東京の場合も、決して例外ではなく、むしろ近代の東京の歴史は、そうした土地の歴史の集積として見るべきで、都市の歴史とは、すなわち土地の歴史でなければならないと結論付けました。
さらに鈴木は、ゲニウス・ロキという言葉を引っ張り出してきて、そうした土地のもつ霊力ともいえるような力に着目します。ゲニウス・ロキとはラテン語の「geniusloci」。geniusは英語のspirit(精霊、魂)、lociはlocos(場所)で、一般にこれは土地霊とか土地の精霊と訳されるのですが、鈴木は、土地から引き出される霊感、土地に結び付いた連想性、土地がもつ可能性という意味を込めて、「地霊」と訳し直します。
「地霊(ゲニウス・ロキ)という言葉のなかに含まれるのは、単なる土地の物理的な形状に由来する可能性だけではなく、その土地のもつ文化的・歴史的・社会的な背景と性格を読み解く要素もまた含まれている」というわけです。都市というものは、綿密な土地利用分析と権力者たちの構想だけでつくられているわけではなく、目に見えない潜在的構造、集合的無意識も働いているという。鈴木博之は、こうして都市をとりまく網状組織とそこに深くかかわる土地の、きわめて具体的な言説の編成体の分析として、都市論を再構築するのです。今にして思えば、
『東京の<
地 霊
>』は、まさに東京の空間論的転回を先取りする試みではなかったかと思うのです。
今号では、三つの視点から地理の新しい見方、空間論的転回について考えます。
都市の形成、その中心に寄り添うように存在し続けた場所に「花街」がありました。「花街」は、つねに「語られざるもの」「隠されたもの」として歴史の隙間に埋もれていた場所でした。近代都市の形成とその過程に介在する「花街」の役割について、地理学の立場から分析しているのが立命館大学文学部准教授で文化地理学を専攻する加藤政洋氏です。土地空間上のさまざまな事象、配置、位置、関係を、地理的な視点に立って捉える文化地理学の方法論を解説していただきながら、いわゆる「空間論的展開」について言及していただきます。
自分の住んでいる場所や地域を指すごくありふれた語「郷土」。このありふれた「郷土」は、まさにそのなんの変哲もなさが、自明であることが、じつは大きな問題だというのです。「郷土」は、何よりも近代国民国家の形成と連動して人工的に「つくられた」概念であること。また、「郷土」形成のプロセスを稼動させる枠組みがいったん成立すると広範囲にその影響が及ぶこと。この大きく二つの理由により「郷土」は、土地空間上の政治力学、場所と記憶の問題を考えるうえで、重要な意味をもつといいます。特定の空間的範囲でありながら、マルチスケールな様相を呈する「郷土」概念・心象が、どのように構築され身体化されてきたのでしょうか。文化地理学的観点からそれを明らかにすべく研究しているのが神戸大学大学院人文学研究科准教授で地理思想が専門の大城直樹氏です。政治的な産物である「郷土」概念の形成過程について、大城直樹氏に郷里である沖縄を事例に論及していただきます。
東京都東久留米市の滝山団地では、七〇年代戦後民主主義の旗の下、全生研(全国生活指導研究協議会)が「学級集団づくり」を実践していました。理想に燃えたその「自治的な共同社会」=コミューン、しかし子供の目には、それはまったく異なったものとして映っていたのです。『滝山コミューン一九七四』は、当事者の証言をもとに全生研の実態に迫ったドキュメンタリーですが、都市空間と重層的にかかわる政治性について体験的なまなざしを通して考察する「空間政治学」の実践でもありました。その著者である明治学院大学国際学部教授で日本政治思想史が専門の原武史氏に、土地の記憶と言説の歴史に切り込む方法としての「空間政治学」についてお話しいただきます。(佐藤真)
参考文献:
『都市空間の地理学』ミネルヴァ書房、2006
|