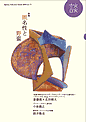| 
�������̈Ӗ���₢����
���哽���f����
�@P2P�̃t�@�C�������\�t�g�EWinny�̍�҂����쌠�@�ᔽ�̋^���őߕ߂��ꂽ���ƂȂǂɂ��AIT�i���Z�p�j�ɂ����铽�����ɁA�S���W�܂��Ă��܂��B�������̖����l���鎞�ɁAIT�̐i�W�������炵���l�b�g�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ȃ����Ƃ������Ƃł��傤�B����������A�C���^�[�l�b�g�ɂ���ĊO���Ƃ̏펞�ڑ���������O�ɂȂ������Ƃ��A�������ɓ������ւ̊S�����߂Ď�N�����邱�ƂɂȂ����Ƃ������Ƃł��B�����ł́A�������ɂ��čl���܂��B
�@
�@�u2�����˂�v�Ƃ��������f��������܂��B���������̃A�N�Z�X���͎��ɂ���Ĉꁛ�������邱�Ƃ�����Ƃ�������Ȍf���ł��B�C���^�[�l�b�g�����������uJapan
Access Rating�v�́u�N�ԃ����L���O�i����N�Łj�v�i������ЃA�C�E�G�X�E�e�B�j�ɂ��ƁA�u2�����˂�v�̃h���C�����Ƃ̃A�N�Z�X�ʂ͑S�̂Ŏl�ʁA�R�~���j�e�B�f���n�ł͑��ʁA�܂��A�����T�C�ggoogle��Yahoo!
JAPAN�����N�ɔ��\�������{�����̌����L�[���[�h�ł����ʂł��B
�@�u2�����˂�v�ɂ́A���܂��܂ȃW���������A�J�e�S���[�ʂɕ��ނ���Ă��āA���̐��l���ȏ�B�܂��A�f�����l�����ȏ�A�X���b�h�i�f����=�̃g�b�v�y�[�W�Ɍ����b��j�͂����ƘZ�������ȏ�A�g�b�v�y�[�W��������Ă���X���b�h���܂߂�ƈ�Z���Z�������ȏ゠��Ƃ����܂��B�u2�����˂�v�͂܂��ɂ������̂悤�ȃT�C�g�ł��i*1�j�B
�@�N�ł���y�ɐV�����X���b�h�𗧂��グ�邱�Ƃ��ł��A���[�U�[���m��Q���ӎ����邱�ƂȂ����R�Ɉӌ�������������B������肩��r�W�l�X�A����y�A�ʂĂ̓A�C�h���╗���܂ŁA�Ƃɂ�������Ƃ�����b�肪��l���ԋx�݂Ȃ��������܂��B�u2�����˂�v�̍ő�̖��͂́A�Ȃ�Ƃ����Ă����̓����ŏ������߂�Ƃ����Ƃ���ɂ���܂��B
�@�u2�����˂�v�������グ��ꂽ�͈̂����N�܌��B���̂��傤�Lj�N��ɐ��S�o�X�W���b�N�������N���܂������A�u2�����˂�v�͂��̎��������������ɂ��āA���Ԃ̒��ڂ��W�߂�悤�ɂȂ�܂����B�Ƃ����̂��A�Ɛl���u2�����˂�v�ɔƍߗ\������������ł������Ƃ��킩��������ł��B�u�l�I�ނ����v�Ƃ�����ȃn���h���l�[�������邱�ƂȂ���A���ꂪ�����̌f���ł��������Ƃ����ڂ��ꂽ�̂ł��B�����l�b�g�Ɗւ��̏��Ȃ��w�ɂ��u2�����˂�v�͋�����ۂ�^���܂����B
�@�u2�����˂�v�̍ő�̓����ł��铽�����́A�������A����Ŏs���ɋ����s�M������������Ƃɂ��Ȃ�܂����B���Ƃ��A�X�g�[�J�[��s�R�҂̓��������A��苭�����|��������o���悤�ɁA�������ɂ͍D�܂����Ȃ��C���[�W�����܂Ƃ��B�������Ƃ������t����A�ƍ߂Ƃ̊֘A��A�z����l������ł��傤�B
�@���S�o�X�W���b�N���������������ŔF�m�x�����܂����悤�ɁA���̓�������ƍ߂ƌ��ѕt���Č��悤�Ƃ��镗��������܂����B���ہA�u2�����˂�v�ł́A���̌�ƍߗ\���������Ƃ̓��������A���_�����ŊǗ��҂��s�i����Ƃ��������Ƃ��N���܂��B�V�X�e����̕ύX���������āA���݂ł́A�����f���Ƃ�搂��Ă͂�����̂́A���S�ȓ�����������Ă���킯�ł͂Ȃ��ƌ����Ă��܂��B
�������̌���
�@�u2�����˂�v�̌����́A�����ʂ̃��f�B�A�����ڂ��Ă��܂��B���Ƃ��ƃ}�X�R�~�����グ�邱�Ƃ̂Ȃ��悤�ȃl�^�̏W�Ϗ����u2�����˂�v�ł����B�Ƃ��낪�A�}�X�R�~�����̃��\�[�X�Ƃ��āu2�����˂�v���g�p���n�߂Ă���̂ł��B���Ƃ��A�u�����d�]�ϑ����v�i�G���w���N!�x�j�Ƃ����R����������܂��B�b��̃l�^���u2�����˂�v�̃X���b�h�̏������݂�����p���A����ɃR�����g��t��������Ƃ������̂ł��B�����Ȃ�ƃ}�X���f�B�A�u2�����˂�v�Ƃ����\�}�A�܂��A�}�X�ɑ��鎩�R�ȓ����̔����̏�u2�����˂�v�Ƃ����ʒu�t������ؓ�ł͂����Ȃ��Ȃ�܂��B
�@���������l�@����ɂ������āA�܂����́u2�����˂�v���Ƃ肠���܂��B
�@��N�A�G���w���E�x�i11�����j�Ɍf�ڂ��ꂽ�u�o�����{�̃i�V���i���Y���v���b��ɂȂ�܂����B�Љ�w�҂̖k�c�ő厁���A�u2�����˂�v�ɂ��Ę_�������̂ł��B�せ�N��̏I���Ɂu2�����˂�v�����サ�Ă������ƂƎ�҂̃R�~���j�P�[�V�����̍\���I�ϗe�̊ւ���T��A����̎�҂Ɍ�����u�Ȃ���v�w���𖾂炩�ɂ������̂ł��B�k�c���͂��́u�Ȃ���v�w�����A��i�ł͂Ȃ��ړI�ɂȂ��Ă��邱�Ƃɒ��ڂ��܂��B������ϋɓI�ɘ_���邱�Ƃ����A�Ƃɂ����u�Ȃ����Ă������v�Ɣށi�ޏ��j��͋����v���B���́u�Ȃ���v=�u�ڑ��w���v�́A�l�b�g���݂̂Ȃ炸�������ʂɌ��邱�Ƃ��ł��܂����A�������ւ̊�]�Ƃ������������܂��B
�@�w�k�xno.68�ŃC���^�r���[�����Ă����������֓������u2�����˂�v�ɂ�����R�~���j�P�[�V�����ɒ��ڂ��Ă��܂��B�G���wInter communication�x�ino.48�j�̘A�ځu���f�B�A�͑��݂��Ȃ�7�@���f�B�A�̃I�[�g�|�C�G�[�V�X�i�O�ҁj�v�ł́A�k�c�ő厁�̘_���������u2�����˂�v�ɂ��Ď��Blog�Ƃ̔�r�Ř_���Ă��܂��BBlog�Ƃ́AWeblog�̂��ƂŁA�ȒP�Ɍ����Ɠ��L�`���̃E�F�u�T�C�g�̂��ƁB�킪���ł�Blog�͋}���ɕ��y���Ă��܂����A�Ȃ������{�l��Blog�����u2�����˂�v�ɂ��e���݂������Ă���ƍ֓����͌��Ă��܂��B�����Ă��̗��R���A�������Ɋւ���e�a���A�ԓx�̈Ⴂ���琶�܂�Ă��Ă���̂ł͂Ȃ����ƌ����܂��B��͂�A���̃J�M�́u�Ȃ���v�w���ɂ���̂ł́A�ƍ֓����͐������܂��B
�@�����ŁA�k�c�ő厁�ƍ֓����ɁA�u2�����˂�v�ABlog�A����Ƀl�b�g���ɂ�����R�~���j�P�[�V�����Ƃ��Ă͖����ł��Ȃ��`���b�g�ɂ��āA�������Ɗ֘A�����Ęb�������Ă��������܂��B
�g�̂Ɠ�����
�@�J�~���O�A�E�g�Ƃ������t������܂��B���Ƃ��Ƃ́u�Ⴂ�������Ќ��E����v������Ƃ����Ӗ��ł������A���݂ł́A�u�������A�������ҁA�G�C�Y�A�K���Ƃ����������h�̗���A��`�ł��邱�Ƃ����ɂ��邱�Ɓv�Ƃ����Ӗ��Ŏg����ꍇ�������悤�ł��B�����h�ɑ����邱�Ƃɂ�鍷�ʁE�Ό����Ȃ������߂ɁA����B���Ă������Ƃ�i��ŘI�ɂ���B����������A�v���C�o�V�[�������Č��\���邱�ƂŁA���ꂪ�B���K�v�̂Ȃ����̂Ƃ������Ƃ𑼎҂ɗ��������邱�Ƃ��ƌ����܂��B
�@�v���C�o�V�[�iprivacy�j�́u�����A�������A�܂��͎��I�Ȑ����v�̂��ƁB����̓��������I�ɂȂ鎞�A�������̓v���C�o�V�[���N�Q���ꂽ�Ɗ����܂��B�J�~���O�A�E�g�́A�t�Ɏ��瓽���ł��邱�Ƃ��������B�܂�A���҂ɂ��N�Q�����ۂ��Ȃ��Ƃ������Ƃ��A���ɂ��邱�Ƃł��B
�@�����ꁛ�N�ȏ���O�̂��ƂɂȂ�܂����ATV�i��҂̈팩���F��������K���ł���ƍ������āA�傫�Ȕ������Ăт܂����B�팩����TV�J�����Ɍ������āA�K���Ɠ����Ɛ錾���܂����B�팩���́A����̃v���C�o�V�[�����\�����̂ł��B�������A���̐�������A����ɂ�TV�͈팩�����K���Ƃ̓����ɔs�ꂽ���Ƃ������邱�ƂɂȂ�܂����B
�@�팩���̍s�������f�B�A�̓J�~���O�A�E�g�ƌ����܂����B�ނ́A�K���Ƃ����i�B���Ă����j�v���C�o�V�[�������Č��\��������ł��B�������A����̐g�̂��K���ɐI�܂�Ă��āA����Ɛ키�Ƃ������Ƃ��A�v���C�o�V�[�Ƃ����̂ł��傤���B�m���Ă��Ȃ��͂��̎���̓��̂̔閧��I�ɂ����Ƃ����Ӗ��ł́A�m���Ƀv���C�o�V�[�̗̈�ɑ����邱�Ƃł��B�������A�����G�Ƃ��邱�ƁA�܂�A�����̐키���肾�Ɛ錾���邱�Ƃ́A���͂₻�ꂪ����̓��̂ł͂Ȃ����̂Ƃ��đ�����ꂽ���Ƃ��Ӗ����Ă���Ƃ͂����Ȃ��ł��傤���B�a�C�ɂȂ邱�ƂƁA�a�C�ł���Ɛ錾���邱�ƁB���̗��҂̊Ԃɂ́A�������Ȃ��[���a�����݂��Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł��B����Ȃ��Ƃ��l���Ă������ɁA���̂悤�Ȍ��t�ɏo��܂����B
�@�u��`�q������̂̎c����̂��͂����ăv���C�o�V�[�̗̈悩�ۂ��Ƃ����c�_�͓I���O���܂��B���܂�Ȃ���̓��́A�a���́A���ɂ䂭���̂́A�l�i�I�S���I��̂��j�]����������Ƃ���ŏo�����Ă��邩��ł��B������A��̘_���ׂĂ��̂āA�܂������ʂ̃A�v���[�`��҂ݏo�v���Ȃ��Ƃ����Ȃ��B�i*2�j
�@ �����ّ�w��w�@��[�����w�p�����ȋ����E����`�V���͂����q�ׂāA�u��̂���炸���̂���邱�Ɓv���d�v�Ȃ̂��ƌ����̂ł��B
�@�u�a�C��鍐����邾���ŁA���邢�́A�r�I�X����E���������Ă���l�Ԃ����邾���ŁA�r�I�X�̌��݂�H���j��]�[�G�[���_�Ԍ��ċ��|����B�����Łi�c�j���|��S���I�ŎЉ�I�ȕs���ɓ]�����A��-��������ϗ���Љ�\�z��`�ɂ������āA�r�I�X�̌����B�����Ƃ���B���邢�́A�r�I�X�̌����Z�L�����e�B�E�z�[���Ə̂��āA���X�N�Љ�̃r�I�X��s������v�i*3�j�B
�@�]�[�G�[�ƃr�I�X�́A�C�^���A�̐����N�w�҃W�����W���E�A�K���x���̊T�O�ŁA�ȒP�Ɍ����ƃ]�[�G�[�͐����I�g�́A�r�I�X�͐����I�g�̂��Ӗ����܂��B�������̐g�̂́A�]�[�G�[�ƃr�I�X�Ƃ�����̑w�ɂ���ĊǗ�����Ă���Ƃ����̂��A�K���x���̍l���ł����A���̓A�K���x���̍l�����g���Ȃ���A�����I�g�̂Ƃ���������H���j���ĕ\��鐶���I�g�̂��̂��̂��a�C�̐g�̂��ƌ����̂ł��B�����ł���Ƃ���A�a�C����邱�Ƃ͉����Ӗ�����̂ł��傤���B�]�[�G�[����邱�ƂȂ̂��A�r�I�X����邱�ƂȂ̂��B�a�C�ɂȂ邱�ƂƓ������̖�肪�A�����ɂ͉�������Ă��܂��B���ɁA�g�̂����ɁA�a�C�ɂȂ邱�Ƃƕa�C����邱�ƁA�������ƃv���C�o�V�[�̊ւ��ɂ��Ă��������܂��B
�u�[���E�g�������X����v�Ɠ����� �@
�@����ɂ��A�����s�̊Ď��J�����̐��͂��悻������B�V�h�w�ƒr�܉w���ӂ����ł݂Ă���������ȏ�ݒu����Ă���ƌ����Ă��܂��B�ŋ߁A�a�J�Z���^�[�X�ɐݒu���ꂽ�h�[���^�Ď��J�����́A�O�Z���x��]����S���ʌ^�ŁA�B�e���ꂽ�摜�́A�a�J�x�@���ƌx�����{���̐������S�����ۂɑ��M����A��l���ԑ̐��Ń��j�^�[�Ď�����A�^��L�^����Ă���Ƃ����܂��B�n���S��JR�w�\���A���X�X��R���r�j�A�t�@�~���[���X�g�����ɂ��Ď��J�����̐ݒu���i��ł��܂��B�������̐����́A����A�Ď��J�����ɂ���ĕ�͂���Ă���̂ł��B
�@�Ď��J���������̗��R�̑��ɋ�������͔̂ƍߔ������̑����ł��B�ƍ߂�e������s������邽�߁A�Ď��J�����͕K�v���Ƃ����킯�ł��B���ہA�����s����o�����u�����s���S�E���S�܂��Â�����āv�ł́A�u�ƍ߂̖h�~�ɔz���������̐����v�Ƃ��āA�x�@�̎w���ɂ��������ēs���S��ɁA�Ď��J�����̖Ԃ̖ڂ�߂��炷���Ƃ���߂��Ă��܂��B�������A�Z�L�����e�B�Ǘ����ړI�Ƃ͂����A�u�ƍ߂̖��R�h�~�v�Ƃ����l�����́A���{�I�Ȗ���s��ł��܂��B
�@�u�s�s���������ł���ꍇ�ɁA�ƍ߂͋N����ׂ����ċN����B�ƍ߂𖢑R�ɖh�����߂ɂ́A�ƍ߂ދ���̂��������������E�ݎ��K�v������v�B�u�ߔN�̔ƍߊw�̗̖�ł����Ƃ��e���͂��������_���v�ɃW���[�W�E�P�����O�́u���ꂽ���v���_������܂��B���̎�|�́A�ƍ߂̗\�h�ɂ���܂��B�����āA���̘_�������~���Ɏ��s�Ɉڂ������̂��u�[���E�g�������X����v�ł����B�u�[���E�g�������X����v�Ƃ́A�x�@�ɂ��\�h�I�����܂��O�ꂳ���邱�Ƃɂ���Ē������ێ�����s�s����ł���A�せ�N��̃j���[���[�N�ɓ���������̐��ʂ܂����B
�@��㏗�q��w��C�u�t�E���䗲�j���͒����w���R�_--���ݐ��̌n���w�x�i�y�Ёj�ł��́u�[���E�g�������X����v�ɂ��āA���̂悤�ɕ��Ă��܂��B
�@�u�X�H�ł̂�����Ƃ��������𗐂��s�ׂ�e�\�ȍs�ׁiincivilities�j�ɂ������Ċ��e�ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��B����Ȃ������ȐU�镑�����X�H�����|���A�U�����̂���q����ibeggars�j�r�A�z�[�����X�A�q���t�w�r�A�����ς炢�Ȃǂɏ�����^���˂Ȃ�Ȃ����A���ꂪ�X�̈��S���ɕK�{�ł���B�q�ƍ߂͖������̋A���_�r�Ȃ̂�����B�i�c�j�ƍ߂Ɩ������͂����łȂ��炩�ȘA������`���̂����A���̔��z���q�[���E�g�������X����r�ɑ���ȉe����^���邱�ƂɂȂ�v�B
�@�ƍ߂���g����邽�߂ɂ́A���e�ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��B���̂��߂ɂ́A�Ď��̎�����߂Ă͂Ȃ�Ȃ��B�������⍬���Ɣƍ߂������ł��W����̂ł���A�������ɒ��������邱�ƁB�u�[���E�g�������X����v�̎v�z�́A����������A�s�s�̒����𗐂�����̂��铽���I�Ȃ��̈�@���邱�Ƃ��Ƃ����܂��B
�@�킪���ŋ}������Ď��J���������Ă�����̂́A�ق��Ȃ�ʓ����I�ȑ��݂ł͂Ȃ��ł��傤���B���䗲�j���ɁA�u�[���E�g�������X����v�������ɁA�s�s�Ɠ������̊W�ɂ��Ă��f�����܂��B�@�i�����^�j
*1�@����w��w�@�o�ό����ȁE�����^�G�ق��u2�����˂錤���������Łv�i2002�jhttp://www2.econ.osaka-ac.jp/~matumura/pukiwiki.php?%A3%B2%A4%C1%A4%E3%A4%F3%A4%CD%A4%E
B%B8%A6%B5%E6%20%B2%FE%C4%FB%C8%C7
*2�@����`�V�u�푈�@�B�����邽�߂Ɂ@�w��̃v���g�[�x�̓ǂݕ��E�g�����v�G���w��x3-4-11������
*3�@����`�V�u�s���̃r�I�X�A���|�̃]�[�G�[�v�G���w�����C�J�x36-7�������� �@�@
|