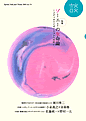| ![editor's note[after]](img/editor_after.gif)
再生医療に何を期待しているのか
身体が資源化する。しかも、その資源の供給源は圧倒的に女性である。女性のからだがいまや人類とその未来にとって重要なストックになりつつある。そして、それを強力に後押ししているものこそ現代の医療に他ならない。現在、医療現場では再生医療に対して大きな期待が集まっているが、この再生医療がまさに身体の資源化の途を拓く立役者である。再生医療のまなざしは、真っ直ぐに女性のからだ、とりわけ子宮と胎盤に向けられている!
粥川準二氏の言葉は、衝撃的であった。先端医療の現場で、今何が起こっているのか。そして何が求められているのか。粥川氏が関係者への取材から得たものは、驚くべき事実であった。急激な勢いで進行する医療化(メディカライゼーション)。その目指すものは何か。それは私たちをどこへ連れ出そうというのか。まさしくそれは身体を徹底的に商品化し収奪する社会である。
身体は資源としての価値のみに還元される。そこでは、身体におけるビオス的側面は見事にはがれ落ちてゾーエーそのものと化す。ゾーエーという剥き出しの身体だけが求められるのである。「生きている」ことが、そこでは決定的な意味をもつ。「生きていてほしい」と願うのは、他ならぬ生-政治なのだ。「いのち」が何よりも尊いのは、それが大切な資源だからだとしたら、なんというパラドクスだろう。
粥川準二氏の議論を改めて整理してみよう。
体細胞クローン動物の誕生、ヒトES細胞の樹立、ヒトゲノムの塩基配列の解読という同時期に確立されたバイオテクノロジーの三つの技術革新が、先端医療を飛躍的に発展させたという。とりわけES細胞は、身体のあらゆる臓器や組織に分化する「多能性」と無限に増殖する「不死性」という二つの大きな特徴をもち、万能細胞などと呼ばれる夢の細胞である。ES細胞の樹立は、他の二つの新技術と組み合わされることによって再生医療への応用が期待されている。再生医療とは、患者自らの再生能力を活かす医療で、従来の臓器移植や人工臓器に代わる新技術だ。クローン技術とES細胞の技術が組み合わさった医療モデルをセラピューティック・クローニングというが、再生医療研究の中でもとくに注目される医療技術である。再生能力を活かすということから、一見再生医療はバラ色の医療技術のような印象を与えるが、じつはいくつかの大きな問題を抱えている。その一つは、受精卵であれ未受精卵であれ基本的には卵子を使用するところにある。つまり、女性の身体からしか採れない細胞を使うことを前提とする医療技術なのである。また、そうした卵子の供給には、基本的に対価は支払われない。原則的に無償である。要するに、再生医療は、女性の身体を供給源とする医療技術であり、必然的に身体の資源化、いのちの商品化を促進することになる。さらに問題なのは、そうした技術に対する十分な検討がなされぬままに技術だけはどんどん進んでしまっていることだ。クローン技術に関する規制もその効力を失っている。
いまや、身体は人類にとって化石燃料にも匹敵する重要な資源となった。しかし、繰り返すまでもなくそこでターゲットとなる身体は、女性の身体である。人類の未来を拓くものとして期待される再生医療であるが、裏返せばそれは、女性の身体、からだ、いのちを供給源とする資本主義の新たな戦略拠点なのだ。私たちは、医療(技術)のいわばこの影の部分をしっかり見据えておく必要がある。むろん、これは医療に限ったことではない。そもそも科学技術というものは多かれ少なかれ輝かしい表の顔とは裏腹に、常に暗部ともいえるような影の顔をもっている。そのことに十分注意を払う必要があるということだ。この科学技術の二面性については、次の小泉義之氏と金森修氏の対談においても重要な争点となっている。後ほどもう一度検討しよう。
生命の序列とゾーエー 粥川氏は、インタビューの最後で身体の資源化と優生思想の関係についても触れられた。これまで優生思想は生殖技術との関わりで議論されることが多かったが、セラピューティック・クローニングにおいても同質の問題が浮上してくるというのである。卵子、受精卵、体細胞を医療目的に使用する場合には、必ずその質が問われるはずだというのである。研究材料になるものもあるだろうが、治療が目的である場合はやはり感染症や遺伝病のヒトの卵子や受精卵、体細胞の使用は避けられるだろう。健康なヒトの細胞はやはりニーズが高いに違いないだろうから、そうであれば優生思想が入り込んでいると見ていいのではないかという疑念である。美味しい(質の良い)食肉を効率良く生産するためにクローン動物はつくられたという面がある。それと同じような構図が見て取れるということだ。身体を資源として捉え直す。たとえば、良質の食肉を生産したいというのと同様に私たちはその「質」を問うようになる。そこに現出するのは、私たちの内なる優生思想かもしれない。
この内なる優生思想をどう捉えるか、そしてそれがいのちをめぐる科学技術にどのような作用を及ぼすのか。小泉義之氏と金森修氏は、この身体が資源化するという現状を踏まえながら、身体の「質」という問題から議論をスタートさせた。「ゾーエー/ビオス」という区分は、身体の「質」を問い、さらにそれを序列化するというところへ踏み込んでいく概念装置として捉え返すことができるだろう。対談のポイントを挙げてみると大きく四つあった。一つは、ビオスはゾーエーを新たな価値物として扱い出したこと。二つ目は、生命倫理には二つの顔があり、身体(の資源化)はその両面から分析される必要があるということ。三つ目は、積極的優生論は治療的介入の可能性を開くということ。四つ目は、ゾーエーをいかに引き受けるかということ。
まず、ゾーエーとビオスの理解の仕方がお二人では違っていることに注意しておきたい。小泉氏は、「生きるに値しない生命」の「生きる」がビオスで「生命」がゾーエーと区分けしたうえで、身体(人体)の資源化という文脈において、ゾーエーが新たな価値物として扱われ始めていることに注目する。それは現代の生-政治が身体そのものに介入していることを示しているという。
一方、金森氏の見解はこうだ。一般的な見方とは少し異なり、より根源的なものをむしろビオスに見出し、ビオスの中で生命は質的な序列をもっているとする。したがって、ゾーエーよりビオスの方がずっと重要だというのだ。そうした前提にたつとQOLを重要視することが障害者差別につながるという議論は納得できないという。QOL、すなわち「質」の序列化を行っているのはビオスであって、QOLはビオスにとって根幹ともいえる概念だと主張する。それに対して、小泉氏は今いわれているQOLは、ごく普通のきわめて単元的な価値を「質」の基準に置いているのが問題であり、障害があるということは「質」が低いと見なされる。まさにその構図が問題なのだ。「人間の尊厳」という言葉も同じである。ただの生命体であれ延命することに意味があるという言葉の先にあるものは、ゾーエーとしての身体だ。生-政治は、ゾーエーのとくにその資源的な側面だけをすくい取る。
金森氏は、「人間の尊厳」という概念をもち出してきた生命倫理について、昨今展開してきた持論を披露する。これまで生命倫理というと、日本では科学技術の暴走を制御しブレーキをかけるものという認識が一般的であった。しかし、それが生まれた欧米圏(とくにアメリカ)では、そうした側面と同時に「新しい思考可能性の地平を開く」という機能ももっていた。生命倫理は、火を消す水としての役割と火に油を注ぐような煽る役割の両面がある。生命倫理には両面性があるという認識にたつと、たとえば生殖系列の遺伝子改造もある種の可能性を開くものとして捉え直すこともできる。それは、これまでの凝り固まった優生学批判に風穴を開けることにもつながる。いわゆる新優生学とも目される思考実験が可能となるのである。つまり、こうした思考実験も生命倫理学の範疇だというのだ。
そこで三つ目のポイントになる。小泉氏も、遺伝子改造を全面的に肯定する。ただし、それはこれまで私たちが「ある種の人間を長きにわたって生殖から排除し続けてきた」という歴史的事実に基づいて、すべての「障害者の生殖を肯定する」という前提にたてばという限定付きだ。遺伝子改造はこれまでの価値観を転倒させることが可能だから肯定できるというのである。それは、「ビオスのセクシュアリティの価値基準を逆転する技術的可能性を開く」ことにもなるからだ。優生学だからいけないという論理はそれ自体倒錯している。小泉氏は「切り捨て淘汰」という思想のもとに殺人を許してきたことが優生学の欠陥であって、その思想を捨てる「積極的優生学」は肯定されるだろうという。すべての障害者には生きていてもらいたいのである。治療的介入を肯定するという意味でも。それは、人間が「まともな生物に変容する」(『生殖の哲学』)チャンスでもあるからだ。
金森氏は、さすがにそこまで大胆には言わない。ただ、今後人間の身体が変容しサイボーグ化していくことは、人為的な遺伝子改造を待たなくてもありうることで、優生学のある一面は肯定できるだろうという。小泉氏とその点では一致する。しかし、金森氏はそれはゾーエーではなく、あくまでもビオスの欲望と捉えているというところに違いがある。生命の意志のようなものを金森氏は感じとっているのだろうか。小泉氏は、反対にそれをゾーエーの相として捉える。それは意識も意志も働かないような「ただ生きている」だけの生命である。であればこそ、それをどのように引き受けるかが問題になるし、私たちの生きていくうえでの課題もそこにある。ゾーエーをいかにして引き受けるか。それはあえて自ら病人になることなのか。小泉氏も明確には述べていないが、生-政治が私たちの身体の深くまで浸透している状況では、確かに、ビオスを越えてゾーエーのレベルまで立ち戻って考える必要があるのかもしれない。これが四つ目のポイントだ。 ヘルシズムの意味するもの アガンベンのゾーエーとビオスという二分法は、フーコーの生-政治を「身体/生命」の言説をめぐる分析へと読み替え、その脱構築化であったと暫定的に述べておこう。アガンベンによれば、生命、生物、人間、肉体、自然はゾーエーに、また生活、人物、人格、精神、文化はビオスに対応するという(小泉義之)。かつて政治の場は人間に特有のビオスを中心に行われてきた。たとえば、アガンベンの研究対象である古代ギリシアにおいて、それはポリスと呼ばれた場所に他ならなかった。つまり、人格をもち生活をする人間という具体、すなわちビオスが「生き」て何がしか行う場所がポリスだったのである。ところが、近代以降ゾーエーがポリスの領域に侵入してきているという。
「政治はゾーエー、すなわち人びとの生物学的な意味においての生そのものの管理をみずからの統治行為の中心に置くようになる。このようにして人びとの生物学的な意味においての生、あるいは〈生きているということ〉そのものをみずからの統治行為の中心におくようになった政治――これをフーコーは〈生政治(bio
poritique)〉と名づける。そしてこれの解明に着手したのであったが、この〈生政治〉のありようを解明することがアガンベンにとってもまた主題であるようなのである」(上村忠男「閾からの思考――ジョルジョ・アガンベンと政治哲学の現在」)。
生-政治は、フーコーによれば近代特有の政治形態と考えられていたが、アガンベンは、古代ギリシアの世界にすでにその萌芽はあったという。ただし、ビオスからゾーエーへその焦点を移動させてきたことが決定的に重要だというのである(小泉氏の立論もこの議論の延長にある)。言説分析の対象が「身体/生命」に置かれるようになったのはそういう理由からだ。改めて「身体/生命」をめぐる言説およびその空間が問題になってくる。
さて、佐藤純一氏と野村一夫氏の対談は、現代社会において生-政治がいかに私たちの身体の奥深くまで入り込み、意識までも支配しコントロールしているかを明らかにした。「健康」への異常ともいえる私たちの関心は、もはやブームという域を通り越してイデオロギーになっている。ブームではなくイデオロギーとして現代の健康を捉えるべきだというのが、お二人の共通認識である。健康が支配的なイデオロギーとなってしまったのはなぜか、そこにフォーカスを当てると浮かび上がってきたのが言説という問題である。健康イデオロギーあるいは健康言説。もともと実体すらあいまいな健康がいつのまにか一人歩きを始め、私たちの意識や行動を規定し始める。単なる言葉でしかない健康に、なぜ私たちはかくも簡単にコントロールされるようになってしまったのか。そこに生-政治の本当の恐ろしさがある。対談の論点を整理しよう。
まず最初のポイントは、治療医学が公衆衛生化したということだ。佐藤氏によれば、近代医学は、病気を治すことをその目的として発展してきた。病気になったからそれを治療する。だから、治療医学というのである。それに対して、公衆衛生は病気の発現を未然に防ぐことを目的とする。病気そのものではなくその予防が主たる目的なのだ。公衆衛生の考えは、病気になる前にその芽を刈り取ってしまおうというのである。そして、近代医学は、その方向で治療医学から予防医学へとシフトしたのである。なぜそのようにしたのか。理由はいろいろあるが、一つには実体として措定できないような病気、すなわち「病的な状態」という他ないようなものがたくさん出てきたために治療がおぼつかなくなってきたことが挙げられる。また、単に治療に失敗するというケースがいっぱい起こってきたのも理由の一つだろう。そこで未然に防ぐという考えが生まれ、公衆衛生の考え方を取り込むことになったというわけだ。
もう一つ伏線として挙げられるのはリスク概念の導入である。病因が特定できないのであれば、その可能性のあるものをもれなくピックアップして、関係のありそうなものを除去すればよい。確率論の考えを取り入れて、リスクファクターを見つけ出し、それを消していくという方向へ舵をとり直したのである。しかし、ここに大きな落とし穴があった。リスクファクターは統計学的にみれば単なる暗数にすぎない。にもかわらず、医学の公衆衛生化という文脈の中で、それが特定できてあたかも取り出せるモノのように扱われてしまったのである。佐藤氏が問題視する「リスクのモノ化」ということを医学はやってしまう。しかも、野村氏の言うように、リスクファクターの選択自体が恣意的な操作によって行われる。特定病因論と確率論という本来ありえない二つの考え方を、強引に結び付けたのが近代医学だというのである。さらに、そうしたリスクファクターをたくさん抱えている(温床)ものが私たちの身体だとしたのだ。
今日言われる「健康」という言葉の裏側には、野村氏が指摘するように、ここで措定されたリスク概念がぴったりと張り付いている。「リスクのない状態が健康」であるとされるわけだが、リスクのない状態というのは何かといえば、それが健康だという。つまり、自己言及的構造になっているのである。健康が言説であるという理由は、このように、健康を意味付けている当のものが健康そのものであるという、いわば言葉によってそれが定義付けられているという意味からである。
生活習慣病という概念は、今いった「リスクのない状態が健康」という健康言説と、医療における「リスクのモノ化」がまさに交錯するところに出現し、私たちの意識と行動を内部から規定しようとしているという意味で、いまやイデオロギーと呼べるような存在になっている。しかも、もう一つ大きな問題は、そうしたイデオロギー、言説を受容しているのは、じつは他ならぬ私たち自身であるということだ。生活習慣病に顕著に表れていることだが、それを受け入れて待望すらしているのは医療従事者でも国家でもなく、私たち自身だというところに、じつは看過できない最も大きな問題が横たわっている。お二人がそこで声を合わせるように指摘しているのが、いわゆる非正規医療の役割である。非正規医療とは、民間医療や代替医療、統合医療と呼ばれているもので、これまで正規医療(近代医療)の外部に位置するものであった。ところが、近年、リスク概念の導入と健康言説の浸透という状況のなかで(もちろん薬漬け医療といった近代医学への批判も大きな要因)、こうした非正規医療に対する評価が大きく変化し、正規医療に匹敵するような影響力をもち始めている。これまで問題にしてきたような健康概念やリスクの温床としての身体という見方は、正規医療と非正規医療が重なり合い相互補完的に機能する状況で――それが私たちの生活世界に他ならない――、今や完全に私たちの意識の内部に定着しつつある。佐藤氏の言葉を借りればヘルシズムの浸透であり、また、野村氏によれば、それはメタメディカライゼーションの徹底化である。すべての現象を病い/健康の二分法で捉え、その善後策を講ずる。生-政治は、このように私たちの身体を統治するのである。 ゾーエーからビオスへ。そして、今、生-政治はその矛先を逆にビオスからゾーエーへとシフトさせようとしている。繰り返すが、現代社会に深く根を下ろす生-政治は、「生きるに値しない生命」には容赦なく死をつきつけるということはしない。かつて権力は人の「死」をコントロールしてきた。その象徴が死刑の執行である。しかし、今日の権力は、そのような形で「生/死」をもてあそぶようなことはしない。事態は逆である。生-政治は、いのちを囲い込み積極的に生かし続ける。むしろ、生-政治は「生」をコントロールするのである。そして、そのコントロールする主体の座を手放す。コントロールする主体は、その身体を生きるその人自身だ。「生」の自己管理を貫徹させること。生-政治は、このように私たちの身体を統治するのだ。しかし、今日の生-政治は、すでにその先に新たなターゲットを見つけ出している。それがゾーエーであることは、あえて言うまでもないだろう。
現代の医療は、一方で健康の増進を奨励し、他方では身体の資源化を推し進める。ある意味では全く正反対に見えることを同じ手つきで同時に遂行するのである。だからこそ、私たちはゾーエーに最後の拠点を見出す。メディカライゼーションへの抗い。その手掛かりは、じつは生-政治が収奪しようとしているゾーエーそれ自身にある。なぜならば、ゾーエーとはいのち、それも「生きるに値しない生命」としての生命のことだからである。「生きている」ことが、生-政治にとっては、「生きている」ことに対する唯一の、そして最大の抗いでもあるからだ。 (佐藤
真)
|