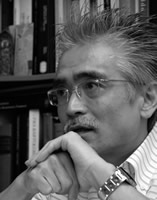| ![editor's note[before]](../no75/img/editor_before.gif)
「変わる」こと、「生きる」こと
「生きている」細胞は映像化できない!?
『談』no.63「移動の記述法」で河本英夫氏(東洋大学文学部教授)は、細胞の動きとそれを外から「動き」として記述することの根本的な違いを次のような比喩を使って説明しています。少し長いですが引用します。
「からだの細胞がいつも動いていることは、誰もが知っていることです。そこでこの動いている状態を写真に撮るとしましょう。細胞の動いている状態を、オートワインダー付きのカメラで連写したとします。ある細胞の時間t1はこれ、t2はこれ、t3はこれ、t4は……、というようにそれらを並べてみる。この一連の写真を今度は早回しにします。そうすると動いているように見えるはずです。この原理を応用したものがペラペラマンガであり、アニメーションです。今、静止することのない連続的に動き続けている空間を記述しようとすると、このアニメーションのような方法で捉えることになります。ある状態aを記述し、次にある状態bを記述し、さらにある状態cを記述し……、という具合に状態記述がずらっと並ぶ。そしてあたかもアニメーションを見るのと同じように、その状態記述の連続として空間が捉えられる。果たしてこの方法によって、動いている状態を記述することができるでしょうか」。
答えはもちろんNOです。それは、この方法がアニメーションと同じであるという理由において、記述したことにはならないと河本氏は言います。外部から見る=観察という方法では、「動いている」という実態を描写できないというのです。
アニメーションが動いているように見えるのは、じつは、そう見ようとしている人にだけなのです。アニメーションは、どんなに動いているように見えても、しょせん単なる静止画のつながりでしかありません。そこには、静止画を素早く連続的につなげると、あたかも動いているように見えてしまうという視覚の性質が使われています。たとえば、点滅する踏み切りの警報器を思い起こしてみましょう。二つの赤いランプが左右に交互に点滅すると、あたかも一つの発光体が左右に移動しているように見えます。ゲシュタルト心理学の創始者の一人であるウェルトハイマーは、その現象を「仮現運動」と名付けましたが、これは知覚がある刺激を運動として捉えようとする性質によるものです。つまり、ここでの「動いている状態」は、見ている側の視覚によって構成されたものなのです。オートワインダーによる連写も同様で、映像によって記録された細胞が動いているように見えるとしても、それは徹頭徹尾見る側による「構成された運動」にすぎないのです。
では、からだの細胞の方はどうでしょうか。からだの細胞は、言うまでもなく、見る側のいかんに問わず動いています。それ自体で動いています。見る側が構成しなくても、からだの細胞は日々途絶えることなく動いています。このように、からだの細胞の動きとそれを記録する映像の動きは、根本のところで全く異なるものなのです。細胞の動きという、私たちにとっては自明と思われているものですら、その記述方法となるとほとんどお手あげの状態です。
動いている細胞……。ここで「動いている」という意味は、「生きている」ことに他なりません。つまり、「生きている」状態を、私たちはまだきちんとした形で記述できていないのです。私たちの日常言語の中に、「生きている」という実態を表す適切な言葉がまだないということを、まず確認しておきましょう。
純粋持続と差異の差異化
アニメーションのように、観察者(見る側)によって構成された「動き」ではない、それ自体で動いているもの。その「動き」に迫ろうとした試みの嚆矢がベルクソンの哲学であることに異論はないと思います。ベルクソンの「純粋持続」は、外部から計量的に捉えるのではなく、「内なる自我の躍動」として、純粋に内側から体験される「動き」を持続という形で概念化しようとしたものでした。その試みが成功しているかどうか、それは研究者によって見解が分かれるところですが、少なくとも「動き」を「持続」と捉え直すことによってそこに内的な展開の契機を見出そうとしたことは、「動き」を「生きている」状態と考える私たちの議論に大きなヒントを与えてくれます。
ベルクソンの「純粋持続」を、現代思想の文脈の中で、「差異化」という概念で読み替えたのがドゥルーズです。ベルクソンの「純粋持続」には、時間の空間化、空間の時間化という哲学上の難問を抱えて煩悶するある種の煮えきれなさが見受けられますが、ドゥルーズはそれを徹底的に時間論として読み込みました。差異の差異化――差異することと差異化されるものとの差異――という形で運動を見て、その繰り返しとして「時間」を捉え直したのです(河本英夫氏)。あるいは、こう言い換えることもできるかもしれません。「差異構造のすべてを持続の側に受け持たせて、差異それ自身であるもの(持続)と差異によって差別されるのみでそれ自身は差異構造をもたないもの(空間)とのあいだの差異と考えなければならない」(木村敏氏)。ドゥルーズは、時間と空間の本性の差異はもっぱら時間の側が担っているとしたのです。つまり、時間と空間の差異、それ自身が時間だというわけです。「動き」あるいは「生きている」状態は、まさしくベルクソン=ドゥルーズにとっては、時間そのものなのです。
映像としてではない生命現象。時間そのものとしての「生きている」という事態。私たちは、このことをどのように捉えたらいいのでしょうか。これまで、『談』では数回にわたって「いのち」について考えてきました。今号では、その「いのち」を「生きている」ものと捉え返し、その重要なポイントとなる「時間」を手掛かりにして考察します。
生きものは、みな「生きたがっている」
「生きるということは不思議な現象であって、生きている以上は生きることそのものを求めていくところがあります」。以前『談』(「身体のなかの進化論」一九九六年)で岡田節人氏と対談された木村敏氏はこう述べました。そして、ドイツの医学者ヴァイツゼッガーの、「生きている」ということを求めるあり方が「主体性」であり、人間だけでなく生きものはすべて主体的に活動している、という考えを紹介しながら、「生きている」という意味には、生物学的な意味だけではなく、「生きたがっている」という行動(動き)が含まれていると指摘したのです。
ヴァイツゼッガーの「主体性」にしても「生きたがっている」という行動という言い方にしても、自然科学の言葉としてある種の馴染みにくさがあることは否めません。とくに「主体性」という言葉には、六○年代に流行した実存主義の残滓が見え隠れします。木村氏自身もそれは認めているようで、「主体性」が使い古されたカビのような言葉であると素直に述べておられました。ただ、そうであったとしてもこれらの言葉は、これまでの生命科学が忘れかけていた重要な側面に光を当てたとして評価するのです。
生命には、生きものである普遍性という軸の他に、もう一つ個別性、多様性という軸があります。その二つの軸のどちらかが欠けても、生命科学は成り立たない。ところが、今の生命科学は普遍性の追求にのみ邁進して、もう一つの軸である、個別性、多様性が軽んじられているという。ヴァイツゼッガーの「主体性」の議論には、まさにその個別性、多様性を生命科学に組み込もうという強い意思が表れていると木村氏は言っています。
対談の中でお二人は、分子生物学の成果を十分理解しながらも、それとは別の新たな動向が出てきているという点で意見の一致をみました。木村氏は、精神医学の立場から、精神医学が脳をターゲットとした生物学的精神医学(バイオロジカル・サイカイアトリー)に傾斜しているのに対して、精神病理学はもっぱら精神面の研究をその対象としてきたところに大きな違いがあったと言います。とはいえ、生物学的精神医学の発展は、精神病理の分野においても自然科学化を押し進め、現在では、薬物を治療に活かす生物学的精神医学をベースにした、新たな精神病理学が芽生えようとしているというのです。
生命論においても「まるで申し合わせたように」同じ動向が見られると岡田氏は述べました。岡田氏は、生命科学が再び生物学へ向かう胎動があるという興味深い指摘をしています。「生命科学は、バクテリアからヒトまで共通の原理を発見しその原理を分子の働きとして説明することによって、人間の経済性の利潤を求めるプラクティカルなところへ直ちに突入」しましたが、今日再び生物学の時代が到来しつつあるというのです。生命科学は、確かに細胞一個一個の普遍性を明らかにしました。けれども、多細胞生物の場合は、生命体であることが基本です。つまり、細胞の集合体が基本になっていて、ある側面からみれば社会であるような性質も見られます。そこで、岡田氏は、生命科学の成果を十分考慮したうえで、そうした多細胞の集合体=社会を組み込んだ、新たな生物学が希求されているというのです。
変化と多様性をどう捉えるか
多細胞生物を細胞社会と見ようという見方も、また単細胞生物でさえも主体として見るヴァイツゼッカーの見方も、生きものを具体的な個体として捉えようとするところに共通性があります。生きものの大きな特徴に、多様性があります。個体としての多様性を論じるためには、分子生物学が明らかにした遺伝子の仕組みだけでは説明できません。遺伝子に還元できない別の仕組みが必要になってきます。
ゲノムと遺伝子の関係は、おおよそ次のようなイメージで考えることができます。ゲノムはHD(ハードディスク)そのものであり、染色体はHDの本体、遺伝子はHDに保存されたデータ(情報)、そして細胞はHDに保存された情報を画像や音声に変換し、再生や録画を行うPCのようなものにあたります。ただ、この説明では、自己複製とタンパク質合成ということは説明できても、もう一つの重要な仕事が説明できません。もう一つの重要な仕事とは、「変化」ということです。ゲノムが、自己複製とタンパク質合成という二つの仕事しかしていなかったならば、生物というのは一つの種類しか存在しなくなってしまいます。人間なら人間だけ、ショウジョウバエならショウジョウバエだけであり、あるいは複製されたクローンだけになってしまう。しかし、言うまでもなく地球上にはあらゆる生物が存在します。多種多様な植物や動物が存在し、しかもヒトを例にとればその一人ひとりが個性をもっています。つまり、生物は個体としての独自性をもって生きているのです(中村桂子氏)。それは、端的に変わりうる存在だということです。変わることが、多様性をつくり出しているのです。
この多様性をつくり出すのも、じつはゲノムの重要な働きです。すなわち、それが「変わる」ということなのです。分子生物学の著しい発展によって、ゲノムのすべてが今や解明されつつあります。その成果を先取りして、「ゲノムの解析完了イコール生命の仕組みがわかった」という短絡した主張も生まれました。セントラルドグマという言い方はまさにその典型でした。しかし、それは、生きものの半面しか見ていません。生きものが「生きている」ということ、「多様性」をもっているということ、さらには、「個別性」をもっているということ、これらには明確な共通性があります。それは、「変わる」ということです。HDは確かにゲノムに似ています。しかし決定的な違いがあります。言うまでもないことですが、HDは「変わる」ことができません。FD(フロッピーディスク)からCDへ、CDからDVDへ、さらにはDVDからHDへ、技術の進歩はその形態を大きく変えました。けれども、この進歩は記録媒体の変化であり、あえて比喩的に言えば、細胞における自己複製とタンパク質合成にあたります。生きものが「変わる」というのは、もっと本質的な変化です。HDを含むコンピュータそれ自体が、気がつくと「龍」になっていた、「東京湾」になっていたというような変化のことです。別言すれば、「質」が変わってしまうことです。ドゥルーズの言う差異化とは、まさしくこの「質」の変化のことでした。この「質」の変化を生きものという文脈の中にどう落とし込んでいくか、おそらく岡田氏の言う新たな生物学、ヴァイツゼッカーの言う主体性は、その道を拓くための思考のツールなのかもしれません。
寿命としての時間
生きものの多様性をつくり出していく時間。それはヒトにとっては、個体の歴史です。より具体的に言えば、人それぞれの歴史、つまりライフストーリーにあたります。生きもの(生物)であるという普遍性をもち、生きもの(種)としての多様性に開かれ、生きもの(個体)としてのライフストーリーをそれぞれが独自性(主体性)をもって生きること、この一切を「生命」というのでしょう。
ところで、ライフストーリーが生きものを考える一つの軸となるとすると、ヒトにとって生涯という意味が重要になってきます。ヒトは、生涯をかけて個性をつくり、多様性をつくり、また種としての子孫を残すわけですから。ライフストーリーとは、「生きたがっている」生命の軌跡そのものだといえます。
ライフストーリーという視点からヒトを改めて見てみると、生きものにとっては不可避な事態について思い知らされます。生きものは、必ず死ぬという事実です。生きものとして生まれた以上、成長し、老化し、やがて死を迎えます。「誕生は死への第一歩である」からこそ、私たちは、「生きたがる」のかもしれません。
寿命としてのライフストーリー、これもまた「生きもの性」を決定付ける重要な要因の一つです。そして、寿命こそ「時間」そのものなのです。私たちは、寿命によって限界付けられたライフストーリーを生きる「生きもの」だということになります。
この寿命についても、分子生物学は大いに寄与しました。さしあたっては、細胞死の発見があります。再生系の細胞と非再生系の細胞の違いから、アポトーシス、アポビオーシス、ネクローシスという三種類の細胞死の方法があり、分裂寿命はほぼ六○回ぐらいと決まっているといいます(田沼靖一氏『談』「老いの生物学」一九九八年)。このことは、生命の連続性をある段階で自らが絶ち切ること、すなわち、細胞に自死のシステムがセッティングされていることを示しています。細胞自身にセッティングされているこの自死のプログラムは、何を示しているのでしょうか。田沼氏は、これはもはや「遺伝子の夢」という他ないものであろうと言います。遺伝子が存続するために遺伝子をつくり直す。それは、いうならば次世代を残すために自己を積極的に消滅させることです。その手段が有性生殖という高度な技術であるならば、それと構造的に一体となったこの細胞死のシステムこそ、生命の本質を表しているといえます。
生命という連続性を保持することを目的にして、あえて個体としての連続性を断つ。生命は、時間によってその生涯を限界付けられ、同時にまた、時間に生命を受け渡すことによって、「生きたがる」自己を獲得しているのです。生命とは、まさに、時間そのものに寄り添い、時間に住み着く「主体性」そのものだといえるでしょう。
今号では、生命と時間を三つの切り口から掘り下げます。まず、生命と寿命の関係について、「生-政治」という視点から考察します。あらかじめ生命は寿命によって限界付けられているにもかかわらず、私たちは常に永遠の生あるいは不老不死の夢に取り憑かれてきました。近代の「生-政治」は、その願望を欲望に変換し、さまざまな場所に備給し続けています。芸術制作の場、またそれを鑑賞するミュージアムも例外ではありません。いや、芸術の場こそある意味で不老不死への欲望を赤裸々に表明する空間だといっても過言ではないのです。いたみ、煤にまみれ、汚れ、朽ち果てようとする作品を保存し修復すること。なんの疑いもなく遂行される修復という行為を正当化させているものこそ永遠の生、不死への渇望なのです。京都大学大学院人間・環境学研究科教授・岡田温司氏に、一見つながりのないように見える芸術制作の場、鑑賞の空間に深く浸透する「生-政治」についてお話いただきます。
次に、ヒトのライフストーリーに深いレベルで関わる記憶について考えます。ヒトの時間意識とは、他ならぬ記憶のことです。現代の記憶研究は、脳科学の進展によって飛躍的に進みました。脳の中で刻まれる記憶としての時間について、東京大学大学院薬学系研究科講師・池谷裕二氏におうかがいします。
三番目は、生命現象の複雑さ、多様さが時間によってもたらされているということについて。生命システム自体が、時間との抜き差しならぬ関係の内にあるという事実について、カオス、複雑系から探求されている東京大学総合文化研究科教授・金子邦彦氏にお聞きします。 (佐藤真)
|